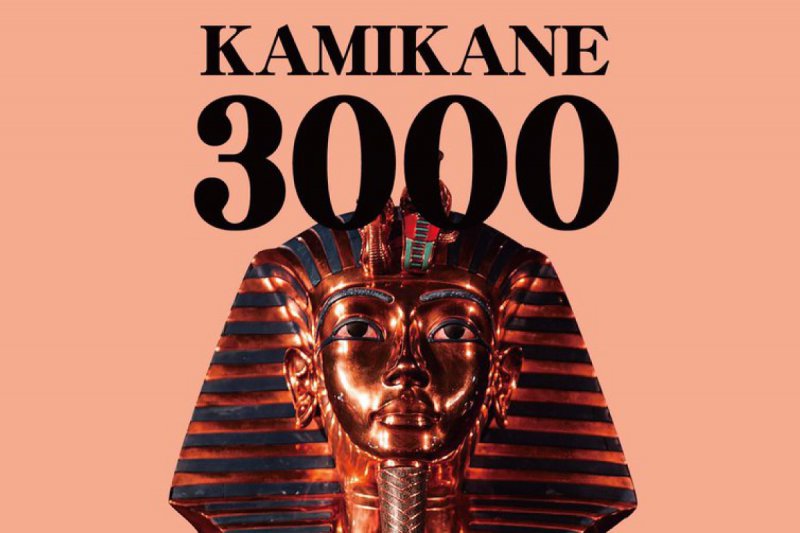stillichimiya特集② ― おみゆきCHANNEL、スタジオ石、深化するソロ活動
第一期を経て、現行体制の五人編成「第二期」へ。
8年ぶりの3rdアルバム「死んだらどうなる」へと至る軌跡。

本記事の剽窃、動画等への転載を固く禁じます。最大限配慮しましたが、それでもなおこの記事の内容に間違いがあった場合、誤った情報がさらにインターネット上に拡散してしまうためです。すいませんが僕はそこまで責任とれないので、必ず一次ソースを参照してください。
この記事は「stillichimiya特集 第一弾」の続編です。多分第一回を読んでないとあまりよくわからないと思うので、読んでない場合は一度そちらに戻られることをお勧めします。
stillichimiya特集① ― stillichimiyaとはいかなる「現象」だったのか? stillichimiya特集③ ― アジア、一宮、三千世界
さて前回は、一宮に戻ったメンバーそれぞれが、stillichimiyaの「部外活動」を始めたあたりの話で終わりました。田我流は2008年11月にソロアルバム「作品集 -JUST-」を発売。YOUNG-GとBIG BENはプロデューサーチーム「おみゆきCHANNEL」として活動を開始。MMMは映像制作という分野に新たに着手。そしてMr.麿は海外放浪中。stillichimiyaはそんな中で富田克也監督らと出会い、同じ頃、インディーレーベルMary Joy Recordingsと契約。そこから「BACK TO 一宮」的スタンスをいっそう明確にし、EP「天照一宮」を発表しました。そのジャケがこちら。

EP 天照一宮(2009)
徐々に山梨に戻っていくメンバーもいる中、2009年、stillichimiyaがMary Joy Recordings(レーベル)に所属することになりました。その時、俺は東京にいたし、レーベル所属のタイミングで彼らのもともとのルーツである、一宮出身の幼馴染ソウルや音楽性というのをはっきりさせようとしていたこともあって、その時点から俺はstillichimiyaではなくなりました。みんな、自分より3つ年が上の人達だったんで、俺からすると「親戚の兄ちゃんたち」みたいな気持ちを抱いていましたね。本当に、いろんな遊びを教えてもらいました(笑)
PONY ネットメディア「SUKIKATTE」でのインタビュー(2017.12.9)*
厳密には、この2009年〜2010年頃にも、まだPONY、KTYらとの活動は継続しているのですが*、およそこの時期を、stillichimiya「第一期の終わり」、そして「第二期の始まり」と位置付けることができるでしょう。田我流はこの2009年頃から、新たな分野に挑戦することになります。空族と富田克也監督が「国道20号線」に次いで手がけた、映画「サウダーヂ」への出演でした。この中で田我流は、右翼かぶれのラッパー「UFO-K」を演じます。

猛 a.k.a. UFO-K
中でも、猛がどうしようもない日常に辟易し、酒に酔いながら歩く帰り道で吐き出した言葉がフリースタイルラップへと昇華されてゆくシーンはまさしく白眉と言えます。そして田我流は、このシーンを「即興」で演じ切りました。宇多丸がこのシーンについて、こう評しています。
この場面、何が素晴らしいってね、この一人の、決して視野が広いとは言えない青年が、でも自分のリアルな不満をラップにして、音楽的に、つまり芸術として吐き出すというこの一場面だけで、ラップ、ヒップホップというもの存在意義が、「この若者にとってヒップホップというものがどういう存在なのか」っていうのが、門外漢にもこの場面一発でわかりますよね。これ以上素晴らしいラップ、ヒップホップの説明はないっていう場面ですよ。
はっきり言って、ヒップホップを扱った、アメリカ映画も含めて、どの映画のどの場面よりもここは、ヒップホップ場面としたらものすごく優れてると思いますね。 TBSラジオ「ライムスター宇多丸のウイークエンドシャッフル」2011年11月5日放送分
また、宇多丸はこの映画を「衰退してゆくコミュニティの現実を、大上段からの正論でなく、そこで生きる者の実感から伝えるという点において真にヒップホップ的であり、ヒップホップという表現の持つギリギリの希望――すなわち、『”もうこの街は終わりだな”ということを”表現”することができる、という最後の希望』を正しく描いている」と評しました。この映画評は最高なので聴いてみてください。そして宇多丸の指摘は図らずも、前回取り上げた、田我流の1stアルバム「作品集 -JUST-」にもそのまま通じるものでした。はっきり言って、ヒップホップを扱った、アメリカ映画も含めて、どの映画のどの場面よりもここは、ヒップホップ場面としたらものすごく優れてると思いますね。 TBSラジオ「ライムスター宇多丸のウイークエンドシャッフル」2011年11月5日放送分
この作中に登場する、田我流演じるUFO-Kが所属するクルーが「ARMY VILLAGE」。そして田我流のほか、ARMY VILLAGEのクルーとして、BIG BEN、YOUNG-G、MMM、KTY、PONY、mestarらが映画に登場しています(Mr.麿の姿は確認できず。映画の撮影期間と放浪の時期が重なっていたため不参加と思われるが、最後のクレジットには名前がある)。

stillichimiya演じるARMY VILLAGE。まだPONYとKTYの姿がある
翌年2010年3月、YOUNG-GとBIG BENは、Mary Joy Recordingsより「おみゆきCHANNEL」としてのフルアルバム「おみゆきさん」を発表。毛色の被らないバラエティ豊かなウワモノと、全編を通して通底する太いビートに、ラッパーとしてstillichimiyaの面々に加え、鎮座DOPENESS、SD JUNKSTAの面々、MONJUらが参加。stillichimiyaのビートメイカーチームの、この時点での集大成とも言える、非常にクオリティの高いものに仕上がっています。

おみゆきCHANNEL『おみゆきさん』(2010)
このアルバムの中におけるハイライトは「ジャングル殺法」でしょう。田我流、BIG BEN、MMM、YOUNG-Gに加えて、PONY、KTY、mestarら、第一期メンバーがフル参加したこの作品では、まさしく第一期stillichimiyaの集大成とも言えるマイクリレーを聴くことができます。
2010年9月19日、THA BLUE HERB 47都道府県ツアーのラストが山梨県であり、その対バンがstillichimiyaだった。
その1曲目として「ジャングル殺法」を披露。
おみゆきCHANNELはこの頃に発売されたPONYの1stアルバム「VERSEDAY」の全面プロデュースも担当。時代を少しくだりますが、さらにPONYは、8ヶ月後の2011年1月、B-BOY PARK 2011 冬の陣で全国優勝。シーンにおいて確たる存在感を発揮します。その1曲目として「ジャングル殺法」を披露。
3年後、PONYはこの優勝賞金を巡るある事実を曲の中で暴露、告発しますが、それはまた別のお話。印象としては、この頃からPONYはstillichimiyaとは別の方向性を進み始めたという感じがあります。
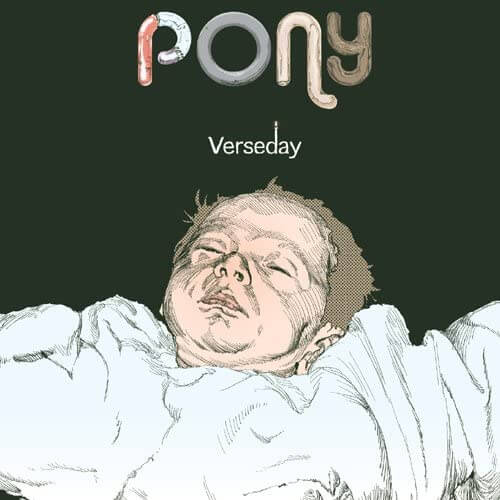
PONY『VERSEDAY』(2010)
スタジオ石とおみゆきCHANNEL
2010年、かねてから映像制作に乗り出していたMMMが、帰国したMr.麿、青木ルーカス氏らと結成したのが、映像制作チーム「スタジオ石」でした。そして「スタジオ石」名義の初仕事として、SD JUNKSTAのWAXの楽曲「いつもそう」のMVを制作します。
彼らがこの頃から本格的に始めた「ヒップホップのMV制作」という分野は、この直後に訪れるYoutubeの時代の到来と合致します。2010年にはスマートフォンの普及率がわずか1桁だったことを鑑みても、この時に始めた「MV制作」がいかに先取的だったかを感じることができます。
スタジオ石は立て続けにMVを制作。当初はやはり荒削りではありましたが、回を重ねるごとに、飛躍的にそのクオリティを高めてゆきます。
それと前後して、この頃のとある夜、富田克也監督はYOUNG-Gからの電話を受けました。以下に富田氏の言葉を引用します。
いつだったろうか、ある晩、いや夜中といっていい時間帯にYoung-G(中村誠治)から電話がかかってきた。彼はHIPHOPグループ「stillichimiya」(スティルイチミヤ)のラッパーであり、その楽曲の殆どを支えるトラックメーカーユニット「おみゆきCHANNEL」のコンビの一人でもある。その声は興奮に震えていた。
(中略)
映画『サウダーヂ』(2011年)は監督の私の故郷でもある山梨県甲府市を舞台にした映画だ。土方・移民・HIPHOPというテーマを主軸に、空洞化や疲弊といったレッテルを張られた現代日本の地方都市を、日本人、ブラジル人、タイ人、フィリピン人などの登場人物達が交錯する群像劇として描いたものである。 私達「空族」はインディペンデント映画製作集団として数年前から活動してきた。活動は国内のみにとどまらず、タイ、ラオス、ミャンマーの、かつてゴールデントライアングルと呼ばれた国境山岳地帯に住む少数民族モン族の不遇な歴史をテーマに映画を作るため現地に赴いたプロジェクトは、「アジア裏経済三部作」として今でもライフワークの様に続いている。 そんな私達にとって、Young-Gからかかってきたその電話は願ってもない内容だった。
「東南アジア最大のスラムと呼ばれる、フィリピンはマニラのトンド地区に、HIPHOPのワークショップをやりに行く」、と。 「トンド、イチミヤ、クゾク、ヒップホップ、エイガ」
オーバーラップするマニラと山梨のストリート 富田克也*
2010年5月に、フィリピン・フランス・ドイツの団体が中心となり、各国のアーティストを招聘のもと、フィリピン、マニラのスラム地区においてヒップホップのワークショップを行い、それを通じて現地の若者をエンパワーメントするという「RAP IN TONDO」なる企画が催されました。そしてきたる2011年度に、その第二回として「RAP IN TONDO 2」の開催が決定。この回から、日本の国際交流基金が新たに加わります。そして日本からのヒップホップアーティストとして参加を依頼されたのが、おみゆきCHANNELの二人でした。(中略)
映画『サウダーヂ』(2011年)は監督の私の故郷でもある山梨県甲府市を舞台にした映画だ。土方・移民・HIPHOPというテーマを主軸に、空洞化や疲弊といったレッテルを張られた現代日本の地方都市を、日本人、ブラジル人、タイ人、フィリピン人などの登場人物達が交錯する群像劇として描いたものである。 私達「空族」はインディペンデント映画製作集団として数年前から活動してきた。活動は国内のみにとどまらず、タイ、ラオス、ミャンマーの、かつてゴールデントライアングルと呼ばれた国境山岳地帯に住む少数民族モン族の不遇な歴史をテーマに映画を作るため現地に赴いたプロジェクトは、「アジア裏経済三部作」として今でもライフワークの様に続いている。 そんな私達にとって、Young-Gからかかってきたその電話は願ってもない内容だった。
「東南アジア最大のスラムと呼ばれる、フィリピンはマニラのトンド地区に、HIPHOPのワークショップをやりに行く」、と。 「トンド、イチミヤ、クゾク、ヒップホップ、エイガ」
オーバーラップするマニラと山梨のストリート 富田克也*

RAP IN TONDO2のポスター。ルフトハンザ航空、エールフランス航空など、
ビッグスポンサーの名前がある
先の富田克也氏の文章はこう続きます。
次の瞬間、私は間髪入れずに何が何でも同行して撮影したいと申し出ていた。聞けばトンド地区は、そこに住む若者たちが結成しているギャンググループ同士の抗争が絶えず、銃撃戦も頻発する場所とのこと。そのような場所にカメラを持って入る事など、この機会を逃したらまず二度と訪れないだろうと直感したからだ。
「トンド、イチミヤ、クゾク、ヒップホップ、エイガ」
オーバーラップするマニラと山梨のストリート 富田克也*
こうしておみゆきCHANNELと、それに同行した富田克也監督は、翌2011年5月、フィリピンはマニラのトンド地区へと旅立ちます。また、この時からおみゆきCHANNELの二人は、現地のヒップホップクルー「TONDO TRIBE」と交流を深めてゆくこととなりました。その時の彼らの様子は、国際交流基金が公開している動画などにも確認することができます。オーバーラップするマニラと山梨のストリート 富田克也*
これ、彼らのYoutubeチャンネルとかじゃないのがいいですよね。お堅めな記録映像なのがインターネットディガーとしてはアツいところです。この時の経験はYOUNG-Gにとって大きかったようで、彼は「アジアのゲットーにヒップホップがある」ということに衝撃を受けました。当時のことをこう語ります。
「マニラのトンドっていうところにいる子供たちに、音作りだとか、ヒップホップのノウハウを教えて欲しいということで、そのプロジェクトに呼ばれて行ったんですけど、現地でリアルなタカログ語のラップを体験して「こんなのがあるんだ!」と衝撃を受けて。
東南アジアがすごくパワーがあることは知っていたけど、それを知ってしまってから、これはフィリピンだけではないはずだと、他の東南アジアのヒップホップをインターネットやCD屋さんのワールドコーナーで探しはじめて」 MIXMAG The Culture Clash: Young-Gがタイに惹かれる理由*
世界の各国では、「日本にヒップホップがある」という事実が驚きを持って受け取られるそうです。しかしそれと同じように、世界各国にはその国の、もといその地域のヒップホップがあるのでしょう。世界各国に実は存在していた「シーン」と、この後stillichimiyaは大きく関わりを持ってゆくこととなります。東南アジアがすごくパワーがあることは知っていたけど、それを知ってしまってから、これはフィリピンだけではないはずだと、他の東南アジアのヒップホップをインターネットやCD屋さんのワールドコーナーで探しはじめて」 MIXMAG The Culture Clash: Young-Gがタイに惹かれる理由*
さて「stillichimiyaとアジアのヒップホップ」の出会いはこうして始まりましたが、この頃田我流もまた、トラックメイカーEVISBEATSとの、運命的とも言える出会いを果たしていました*。
「ゆれる」

EVISBEATS「ゆれる」(2012)
「ゆれる」は実はその、EVISBEATSさんと、他の曲で一番初めコンタクトとってて。で、家のほうに遊びに行ったんすよ。その当時は大阪にEVISさんが住んでて。で、「このビート、今アルバム作ってて、このビートで誰も上手く乗せれないんですよね」っていうの聞かされて。
で、たまたまもう書いてあったリリックがあったんすよ。で、それを乗っけたら、「あ、いい感じじゃないすか」って。で、その場でさらっとサビみたいの歌って、出来上がったっていう。だからたまたまできた曲なんですよ。
Behind the Bars Japan – Red Bull 64 Bars S1 E3/荏開津広*
手元にあったリリックを乗せてみたら、たまたまがっちり合った。そして、その出来栄えに二人で軽く納得していた。しかし、この曲は本人たちが思うほど軽いものではなかったようです。その曲ができた直後、田我流は軽い気持ちでこの曲をDJでかけたそうです。
で、たまたまもう書いてあったリリックがあったんすよ。で、それを乗っけたら、「あ、いい感じじゃないすか」って。で、その場でさらっとサビみたいの歌って、出来上がったっていう。だからたまたまできた曲なんですよ。
Behind the Bars Japan – Red Bull 64 Bars S1 E3/荏開津広*
できて、その次の週にクラブかなんかでDJやる機会があってかけたんですよ。自分で。そしたらブースに人がブワーって殺到して、「これ誰の曲なの?」みたいな。「めっちゃかっこよくない?」ってなった時に、あ、何だこれヤバいかもってなって。これはなんか、俺は何かを作ったかもしれないな、みたいな。
(中略)
なんかその時に、あ、これ、代表曲になるなって実感があったんすよね。明らかに違った Behind the Bars Japan – Red Bull 64 Bars S1 E3/荏開津広*
できあがった直後からブース周辺に人が殺到するほどに「明らかに違った」という「ゆれる」でしたが、この曲にいち早く反応したのは、他ならぬ「スタジオ石」のクルーでした。当時のスタジオ石のウェブサイトには「曲に惚れたスタジオ石が、制作した2人に頼んで映像化させて頂きました」とあります。田我流とは旧知であるはずの彼らもまた、この曲の持つ力にいち早く反応していたのでしょう。2011年6月、スタジオ石は「ゆれる」のMVを撮影します。(中略)
なんかその時に、あ、これ、代表曲になるなって実感があったんすよね。明らかに違った Behind the Bars Japan – Red Bull 64 Bars S1 E3/荏開津広*
EVISBEATS feat. 田我流「ゆれる」のMVはこの2011年の年末に公開され、2021年現在までに1200万回以上の再生数を記録。先述のとおり、この曲は田我流の射程圏を、ヒップホップリスナーの外にまで押し広げることとなります。今にして思えば、スタジオ石がこの時下したMV制作の決断は、まごうかたなき英断でした。
「サウダーヂ」:さらなる快進撃
2011年はstillichimiya飛躍の年でした。富田克也監督のもと、かねてより製作が進められていた映画「サウダーヂ」が海外からも高く評価され、ロカルノ映画祭にて独立批評家連盟特別賞を受賞。富田克也監督はこの映画の制作に際し「平日にトラック運転手をやり、休日に映画を撮る」という生活を1年半ほど続けており、また空族のメンバーめいめいも、手に仕事を持ちながらも制作に参加していました。「サウダーヂ」はこれを皮切りに、ナント三大陸映画祭、高崎映画祭、毎日映画コンクール等、国内外で多数の賞を受賞。国内においても、川勝正幸や宇多丸らから絶賛を受けることになります。
Embed from Getty Images
富田克也、田我流、川瀬陽太。ロカルノ映画祭にて。(GETTY IMAGES)
どうでもいいですが、ウィークエンドシャッフルの「サウダーヂ」評の中で宇多丸が「この番組で以前”墓場のDigger”もオンエアりしたりして」と言及する箇所がありまして、これ多分ポストにぶち込まれたCDなんですよね。先にも触れましたが、この映画の挿入歌としてstillichimiyaが製作したのが「莫逆の家族」。この楽曲のMVもスタジオ石が製作しました。そしてこのMVの冒頭には「映画『サウダーヂ』公開記念映像作品」という表記が挿入されており、つまりこれは、「サウダーヂ」本編と連動した、「作中に登場するヒップホップクルー『ARMY VILLAGE』のその後の物語」という設定が与えられたものでした。
そしてそれを踏まえて ― つまり、「サウダーヂ」本編からのARMY VILLAGEとしての連続性と、stillichimiyaとしての連続性を踏まえた上でこのMVを見ると、最後の最後に登場する人物に、爆笑とともに「いやお前(色んな意味で)いなかっただろ」という盛大なツッコミを入れてしまうことは必至でしょう。見たことない人はぜひ、映画「サウダーヂ」を見てから改めてこのMVを見てみてください。
2011年10月に公開されたこのMVは、この年の年末に行われた「Amebreak AWARDS 2011 BEST VIDEOS」で第1位を獲得。*楽曲の認知経路が急激に動画ベースに切り替わった時代にあって、「スタジオ石」の活動は、―当人たちが狙ってか狙わずか― まさしく時代の潮目を正確に捉えたものでした。

AMEBREAK AWARDS 2011の当時のウェブサイト
そして翌2012年2月、ようやく「ゆれる」の7インチが発売。スマッシュヒットを記録する中で、満を持して発売されたのが、田我流の2ndアルバム「B級映画のように2」でした。
「B級映画のように2」

田我流2ndアルバム「B級映画のように2」(2012)
現在、日本のヒップホップにおいて「名盤」のひとつに位置付けられている作品といっていいでしょう。
個別の楽曲についてコメントを加えるにはいささか紙幅が足りないので控えますが、楽曲ごとにさまざまな切り口を持ちながらも、トータルとして見事な一貫性を持つ、まさしくアルバムのアルバムたる醍醐味を持つ一枚でした。
そしてこの結実には前述の「映画」の経験が影響していたことを、彼は近年のインタビューで語っています。
「B級映画」に関しては、1stと明らかに違うのは、例えば映画とか小説とか、じゃあ描きましょうってなったときに、キャラクターが出てくるじゃないですか。キャラクターってただ漠然とキャラクターが出てくるんじゃなくて、物語を象徴するメタファーじゃないですか、キャラクターって。こういう要素をこの子達が含んでいて、みたいな。その逆算した作り方っていうのを学べたのが大きかったですかね。初めてそういうことをしてみた。
この曲がこういう意味を持ってて、で、全体でこういうコンセプトアルバム、っていうことが、初めてあれでできたですかね。
――それは富田監督とか、映画関係の人と知り合えたのが大きかったですか。
そうですね。サウダーヂっていう映画に出て、その富田監督っていうのが山梨の出身の方で。自分の10個上くらいなんですけど。で、なんかその人たちと撮影……インディペンデントだったんで。その時その映画監督もトラックの運転手しながら映画作ってたんですよ。土日だけ。だから一年くらいかかったかな。一年くらい俺ずっと一緒にいたんですけど。で、なんかやっぱ近くで、他、自分が関係ないシーンも見るわけじゃないですか。一日同じ行程なんで。で、あ、こういうことかもみたいな。で、脚本も何回もこう、変わるわけじゃないですか。第一稿、第二稿、第三稿みたいなので。あ、なるほどね、と思って。こういう感覚で音楽って作れないかな、みたいに俺も思ったんですよね。
Behind the Bars Japan – Red Bull 64 Bars S1 E3/荏開津広*
このアルバムの中から、MVとして4月に「RESURRECTION」が、7月に「やべ〜勢いですげー盛り上がる」が公開。極めて大きな反響を呼ぶ事になります。Mr.麿の初監督作品となる「RESURRECTION」は、映画的な質感で「演者・田我流」の素材の良さを引き出した、非常にクオリティの高いものでした。この曲がこういう意味を持ってて、で、全体でこういうコンセプトアルバム、っていうことが、初めてあれでできたですかね。
――それは富田監督とか、映画関係の人と知り合えたのが大きかったですか。
そうですね。サウダーヂっていう映画に出て、その富田監督っていうのが山梨の出身の方で。自分の10個上くらいなんですけど。で、なんかその人たちと撮影……インディペンデントだったんで。その時その映画監督もトラックの運転手しながら映画作ってたんですよ。土日だけ。だから一年くらいかかったかな。一年くらい俺ずっと一緒にいたんですけど。で、なんかやっぱ近くで、他、自分が関係ないシーンも見るわけじゃないですか。一日同じ行程なんで。で、あ、こういうことかもみたいな。で、脚本も何回もこう、変わるわけじゃないですか。第一稿、第二稿、第三稿みたいなので。あ、なるほどね、と思って。こういう感覚で音楽って作れないかな、みたいに俺も思ったんですよね。
Behind the Bars Japan – Red Bull 64 Bars S1 E3/荏開津広*
また、「やべ〜勢いですげー盛り上がる」は、震災後の閉塞感が覆う時代にあって、突き抜けた馬鹿馬鹿しさをポジティブなエネルギーに転換し、それをもって現状打破の糸口を提示するような、まさしくstillichimiyaにしか作り得ない傑作でした。
アルバム初回盤にはDVDが付属。これはもちろん「スタジオ石」の存在ありきのものだったといっていいでしょう。そして、アルバム内のほぼ全てのトラック制作、トータルのミックスは、おみゆきCHANNEL、およびYOUNG-Gのバックアップによるものでした*。
先にも述べた通り、2012年に発売されたこのアルバムは現在、2010年代のヒップホップを代表するクラシックのひとつと目されていますが、これまでの経緯を辿ると、この作品が結実する背景に、2011年頃までのstillichimiyaのメンバーそれぞれの「部外活動」の存在が浮かび上がってきます。
おみゆきCHANNELの活動、スタジオ石の結成、「ゆれる」のバイラルヒット、富田克也監督との出会い、「サウダーヂ」への参加。これらの延長線の上に「B級映画のように2」はありました。各自の、その一見バラバラな活動が再びstillichimiyaのもとに結集し、そこに結実したひとつの集大成がこのアルバムだった。一見ソロアルバムに見えるこの作品は、実はまぎれもない「stillichimiyaワーク」でした。
離散と集合、深化するソロ活動
「B級映画のように2」発売後もメンバーは各自の活動を継続。スタジオ石は2012年から2013年にかけて数多くのMVを制作。MOROHA「ハダ色の日々」やZEN-LA-ROCK「ICE ICE BABY」、NORIKIYO「仕事しよう」などを送り出します。
BIG BENはソロアルバム「My Music」を発売。フィーチャリングとして呼んだはずの田我流にヴァース中ずっと悪口を言われてキレるという設定の「パーティーは終わらない」は、stillichimiyaらしい出色の出来。
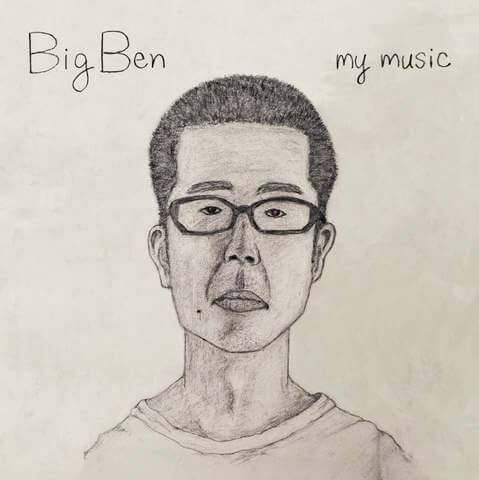
BIG BEN「MY MUSIC」(2012)

YOUNG-G「PAN ASIA Vol.1 ~Unknown World of Asian Rap~」(2012)
とりもなおさず、このMIXはYOUNG-Gが前年2011年の「RAP IN TONDO2」から受けた影響を、ダイレクトに表現したものでした。これについて彼は、GAGLEと共に受けたインタビューでこう語っています。
――トンドに足を踏み入れて以降、アジアのヒップホップを掘るようになっていくわけですよね。
YOUNG-G「そうですね。それ以来いろんなものを聴くようになったし、何よりも人に紹介したいと思うようになって。それでアジアのヒップホップをまとめた『PAN ASIA Vol.1 ~Unknown World of Asian Rap~』というミックスCDを作ったんです」
――あれは名作ですよね。
YOUNG-G「ありがとうございます(笑)。いろいろ調べていくなかで、自分のなかに〈アジア〉というキーワードが出てきて、それをああいう形でまとめたんですよ」
――そこにあったのは〈アジアがおもしろそうだぞ〉という直感?
HUNGER「〈匂い〉みたいなものなのかな?」
YOUNG-G「ああ、そうですね! 確かに〈匂い〉があるんですよ。しかも西欧にはない独特のものであって、僕たちと同じ匂いがした。そこに惹かれたのかもしれませんね」
MIKIKI | HUNGER(GAGLE)とYOUNG-Gに訊く、〈凄いところまできている〉現代のアジアン・ヒップホップ事情*/大石始
また、2013年には、Mr.麿、YOUNG-G、MMMがユニット「EXPO」を結成しEPを発売。ニューウェイヴを感じさせるビジュアルとサウンドを展開します。リード曲の、桂正和「電影少女」へのオマージュともいうべき「電影少年 -VIDEO BOY-」はミュージックビデオも制作されており、ここでは「スタジオ石」のスタッフの一人、青木ルーカス氏の熱演を見ることができます。YOUNG-G「そうですね。それ以来いろんなものを聴くようになったし、何よりも人に紹介したいと思うようになって。それでアジアのヒップホップをまとめた『PAN ASIA Vol.1 ~Unknown World of Asian Rap~』というミックスCDを作ったんです」
――あれは名作ですよね。
YOUNG-G「ありがとうございます(笑)。いろいろ調べていくなかで、自分のなかに〈アジア〉というキーワードが出てきて、それをああいう形でまとめたんですよ」
――そこにあったのは〈アジアがおもしろそうだぞ〉という直感?
HUNGER「〈匂い〉みたいなものなのかな?」
YOUNG-G「ああ、そうですね! 確かに〈匂い〉があるんですよ。しかも西欧にはない独特のものであって、僕たちと同じ匂いがした。そこに惹かれたのかもしれませんね」
MIKIKI | HUNGER(GAGLE)とYOUNG-Gに訊く、〈凄いところまできている〉現代のアジアン・ヒップホップ事情*/大石始

EXPO「EPOTION」(2013)
そうした、交わっては離れ、離れては交わる、離散と集合を繰り返すようなめいめいの活動を経て、グループ結成10周年となる2014年、実に前作から8年ぶりとなる3rdアルバム「死んだらどうなる」は発売されました。
「死んだらどうなる」

stillichimiya「死んだらどうなる」(2014)
やっぱり、中学ぐらいから関係が始まってるから、面白さみたいなのがそのノリのままなんですよね
*Amebreak インタビュー
個人的にはこのアルバム、関連作も含めてstillichimiyaの作品の中で多分一番好きなんですが、同時にとても人に勧めにくいアルバムだったりします。というのも、ヒップホップが「悪いもの」と認識している人にも、「ポリティカルなもの」と認識している人にも ―これは日本における、「ヒップホップ」に対する、ネガティブ・ポジティブ両面からのステレオタイプと言ってもいいかと思います― 、なかなかレコメンドの切り口が難しいというか。
ズンドコ節(2014)
田我流のソロアルバム「B級映画のように2」は、ヒップホップ的な「かっこよさ」を備えながら、ある種の「ポリティカルな作品」としても受け止められ、敢えて穿った見方をするならば、それは「世間一般が抱くヒップホップに対するポジティブなイメージ」とも一致したものでした。しかし本作「死んだらどうなる」はそういうわけでもなくて、「地獄」「ドリフ」「土偶」「竹の子」「サンバ」「カレー」「宇宙」「丹波哲郎」などのトピックをないまぜにしながらも、特にそこにメタファーや暗喩はなく、ただただ内輪的なナンセンスを投げっ放しにしたようなアルバムなのです。田我流はインタビューに答えてこんな発言をしています。
―実は何かあるのか、それともないのか分かんなくなるよね。“生でどう?”の田我流君のヴァースとか、スゴく暗喩にも感じるんだけど、よく考えたらそうでもねえなって。
田我流「いや、確実に何かありますよ。それがなんなのか、俺たちも分かってない」
(全員爆笑)
Amebreak インタビュー*/高木“JET”晋一郎
これ最高ですよね。「じゃあなんでもいいじゃないか」という。ただ前述の通り、僕はこのアルバムが大好きで、それどころか、極めてヒップホップ的なアルバムだとすら思っておりまして。田我流「いや、確実に何かありますよ。それがなんなのか、俺たちも分かってない」
(全員爆笑)
Amebreak インタビュー*/高木“JET”晋一郎
ヒップホップはその誕生から「スラング」と不可分な関係でしたが ―たとえば「B-BOY」なんていう言葉もクール・ハークが作ったものだと言われます―、この「スラング」とは、換言すれば「そのコミュニティにおける言語的コード」に他なりません。ある種の排他性こそがスラングのクールネスでした。かつてNORIKIYOがインタビューの中で語った言葉に、興味深いものがありました。
―今となっては相模原以外の人もメンバーにいるわけで、メンバーにする基準とかはあるんですか?
NORIKIYO「なんだろ……スラングを理解してるとか(笑)。俺たちが言ったことを分かって爆笑してくれるようなヤツが自然とメンバーになる、みたいな。DEFLOやOJIBAHは、それこそ自分からスラング作って笑わしてくれる力量を持ってるから……力量っていうのも変だけど(笑)」 Amebreak SD JUNKSTA(前編)*/伊藤雄介
僕はこのNORIKIYOの発言を、「スラング」が、結束性や排他性、フッド性として機能しているモデルケースとして、かなり意義深いものだと思ってまして。思えば、90年代までの日本のヒップホップは、アメリカのヒップホップのスラング感覚 ―すなわちイルさ― をどう翻訳するのか、という歴史でもあったように思います。そしてその試みにおける最もポップな到達点がたとえばスチャダラパーであり、また最もアヴァンギャルドな到達点が、たとえばBUDDHA BRANDではなかったかと。NORIKIYO「なんだろ……スラングを理解してるとか(笑)。俺たちが言ったことを分かって爆笑してくれるようなヤツが自然とメンバーになる、みたいな。DEFLOやOJIBAHは、それこそ自分からスラング作って笑わしてくれる力量を持ってるから……力量っていうのも変だけど(笑)」 Amebreak SD JUNKSTA(前編)*/伊藤雄介
そうした「イルという概念の翻訳」を経て確立された日本のヒップホップは、その次の段階として、主に2000年代に「フッドに根ざしつつクルーとして活動する」という形態を数多く生み出しました。シーンのフェーズがそっちに向いたと言った方がいいですかね。そしてSD JUNKSTAもstillichimiyaも、その文脈下にありました。これは、日本のヒップホップが文化として消化され、本来のヒップホップの形により接近したものだったのではないかと思うわけです。つまり、フッドやクルーの「ノリ」や「遊び」から、ナチュラルなスラング感覚、スタイル、イルネスが生まれ、それが作品にアウトプットされ始めた。
NORIKIYOのいう「身内にウケるスラングを作り出すスキル」とは、言い換えれば「フッド感」であり、「コード」であり、さらには連帯意識に通じるものなのではないかと、そしてそれこそが「イル」の本質的な部分なのではないかと、そんなことを思うわけです。
で、「死んだらどうなる」なんですが、このアルバムは要するに、そういうものなんじゃないかと思うわけです。
HELL TRAIN(2014)
田我流「そう。これだったら面白いモノ作れるよね、っていうのが共有できるっていうのが」
MMM「っていう話をしなくても、ずっと一緒にいるから、細かいことを説明しなくても、パッと出たニュアンスで、それは面白くなる/ならないっていうイメージが、全員で共有できるんですよね」
YOUNG-G「そうだね。昔ながらの関係から来る、空気感とバランスが鍵を握るっていうか」
MMM「逆に説明できちゃうと面白くないんだよね」
YOUNG-G「ガチガチに考えたモノはつまらん、みたいな」
Amebreak インタビュー*/高木“JET”晋一郎
「フッドをレペゼンする」というstillichimiyaの根幹はもちろんこのアルバムにも通底しているのですが、その上で本作は、それを”武器”として用いることを、始めて「やめた」アルバムでした。そして同時に、完全な五人編成となって初のアルバムで、客演もほぼありません(唯一の例外はついに共演を果たした原田喜照!)。結果、その「身内的グルーヴ感」が ―PONYは彼ら5人編成を「幼馴染ソウル」と表現しましたが― よりピュアに表現された。もちろん、それぞれに部外活動を経た彼らは、8年前の前作とは比較にならないほどのクオリティをもって、それを形作った。MMM「っていう話をしなくても、ずっと一緒にいるから、細かいことを説明しなくても、パッと出たニュアンスで、それは面白くなる/ならないっていうイメージが、全員で共有できるんですよね」
YOUNG-G「そうだね。昔ながらの関係から来る、空気感とバランスが鍵を握るっていうか」
MMM「逆に説明できちゃうと面白くないんだよね」
YOUNG-G「ガチガチに考えたモノはつまらん、みたいな」
Amebreak インタビュー*/高木“JET”晋一郎
とまあ、長々と書き連ねましたが、このアルバムがどう面白いかを説明するよりも、これの面白さがわかってしまったらもう引きずり込まれていると言った方がいいんだと思います。スラング感とは元来そういう引力を持っていて、一見ナンセンスに見えるこのアルバムは、「それ」をこそパッケージングしてしまっているのではないか。かつ、この「身内ノリ=ローカル・スラング=フッド感」は、地方の現状を痛烈にルポルタージュした、田我流のこれまでのアルバムとも相互補完関係にあるのではないか、と思うわけです。然るにこれは、極めてヒップホップ的なのではないかと。
DJ KENSAWの言葉
内容的には本当に、「土偶」「竹の子」「サンバ」「カレー」と、なんでこれを歌にしようと思ったんだという曲のオンパレードなんですが(何度も言うように、そこに意味があります)、そのアルバムをぐっと締めているというか、まとめているのが「帯」だと思っていて、ここには、大阪シーンのオリジナル・ギャングスタ、DJ KENSAW氏から寄せられた推薦文(?)が記されています。これ以上にこのアルバムを、もとい、stillichimiyaを、正確かつ端的に言い表す言葉はないでしょう。いわく、「わしらただ遊んでるだけや」。

DJ KENSAWによる帯文
つづく
stillichimiya特集① ― stillichimiyaとはいかなる「現象」だったのか? stillichimiya特集③ ― アジア、一宮、三千世界